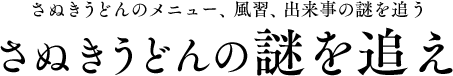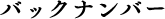恐慌による不況の中、半夏のうどんや屋台のうどん等、うどんに関する小さな話題がいくつか出てきました
昭和2年~5年の香川県は、2年に琴平電鉄(高松~琴平)が開通、4年に屋島ケーブルと塩江温泉鉄道(ガソリンカー)が開通、5年に琴平急行電鉄(坂出~琴平)が開通という「開通ラッシュ」の時期。しかし、昭和4年(1929)に世界恐慌が起こり、その余波で日本も「昭和恐慌」と呼ばれる不況が襲ってきて、新聞には「値下げ」や「就職難」の記事が出てきて、あまり調子のよくない時期でもあります。うどん関連記事は、昭和4年頃から少し増えてきました。
昭和2年(1927)
大正時代の後半あたりから引き続いて「事件記事の中に出てくるうどん店」といった小さいネタが拾える程度の時代が続きます。昭和2年はこの1本だけでした。
電燈消え、電柱に落雷 西浜町の闇黒
3日午後7時頃、俄然篠つくばかりに降りかけた夕立と共に大雷鳴あり。当市西浜町「山口木炭店」前電柱、同町「丸一うどん製造所」前電柱の2個所に落雷したために附近一帯は暗黒の世界と化し、一時もの凄い光景を呈した。
高松市西浜町に「丸一うどん製造所」があったそうです。社名からすると個人経営の製麺屋よりちょっと大きい会社かもしれませんが、この時代は「夜鳴きうどん」や「食堂のうどん」がたくさんあったようなので、そこにうどん玉を卸す商売もご発展だったのではないかと思われます。
昭和3年(1928)
続いて昭和3年も、「事件記事の中に出てくるうどん店」の小ネタが2本だけ。
夜鳴ウドンの車、自動車と衝突 ウドン屋さん火傷
12日午後1時頃、坂出町幸町○○所有の貨物自動車を運転手△△が運転して丸亀市から帰途、坂出町田尾坂で丸亀市西平山町□□(26)の夜鳴き饂飩車と衝突して転覆せしめたが、其の際、□□は沸騰する饂飩湯を全身にあびて治療2週間を要する火傷を負った。
「夜鳴きうどんの車がひっくり返って、26歳の夜鳴きうどん屋の青年が沸騰する“うどん湯”を浴びて火傷を負った」という事件。ここから、「夜鳴きうどんは若者も引っ張っていたらしい」ことがわかりますが、「沸騰する湯」が生麺を茹でる用なのか、ゆで麺を温め直す用なのか、そこは定かではありません。薄利多売の夜鳴きうどんですから、普通に考えれば「ゆで麺」を積んで“夜鳴き”していたのだろうと思いますが。
腕白者が木片で幼児の咽喉部を突刺す 新御坊内の椿事
本籍和歌山県有田郡湯浅町○○(45)は広島県下海軍製油処で稼いでいたが、失職したので11日、妻(31)、長男(4)、長女(2)を連れて高松市内町△△を頼って来た。○○は妻子を片原町新御坊内に待たせて△△氏を尋ねて行ったその後、長男が附近で遊んでいた子供に突き倒され、木片で咽喉部をつきさし重傷を負った。母親は突き倒した子を捕えると共に我が子を抱き上げたが、あまりの出血に驚いてうろうろしていたところ、その傍に居合わせた新御坊前の岡亀ウドン屋の妻□□が「突き倒した子供は自分が知っているから、早く医師に連て行け」と言ったので、百間町の医師方に駆けつけて応急手当を受けた。…(以下略)
事件の内容はさておき、高松市の片原町に「岡亀」といううどん屋があったようです。「うどん屋」とありますから「うどんメニューがある食堂」ではなく、おそらくうどんがメインの「うどん屋」だろうということでおさらいすると、大正から昭和にかけてのこの時期にあった「うどんが食べられる店」は、「メニューにうどんがある食堂」と「うどんをメインとするうどん屋」と「夜鳴きうどんの屋台」と、明治時代から続くおそらく売春をやってた「部屋付きうどん屋」の4種類です。
昭和4年(1929)
昭和4年から、うどん関連記事が少し増えてきました。まず、「事件に出てくるうどん」の情報が2つ。
朋輩殺しの照市と始めて悟らる 饂飩屋から足がつき観音寺署、捜査の手を伸ばす
…(前略)…一夜に4戸を襲うという無類の凶賊、もしこれをそのまま取り逃がすことがあっては県民に合わせる顔がない、いかなる犠牲を払っても必ず逮捕すると管下署員を厳重督励の折柄、新任拝命の所在地勤務○○巡査が9日、観音寺町柳町飲食店近藤サダ方において饂飩を食って店を出た男の人相服装がこの凶賊に似ているとの報告に警察官部は大いに勇気を増し…(以下略)
観音寺市(当時は観音寺町)の柳町で、近藤サダさんという方がうどんを出す飲食店をやっておられました。続いて、大正13年の記事にも出てきた「うどんの卸商」がまた登場。
列車に跳ねられ即死す 松尾村のうどん屋が
大川郡松尾村字鹿庭うどん製造卸商○○(46)は30日午前9時すぎ、自転車にうどん入れ空箱を積んで同郡鶴羽村合地の鉄道踏切りを通過しようとする際、折から進行して来た国鉄高徳線列車132号に跳ねられ即死した。
大正13年に出てきたのは多度津町のうどん卸商(7戸以上)でしたが、今回は大川郡松尾村(現在のさぬき市大川町)のうどん製造卸商。「製造卸」ということは、卸しだけの中間業者ではなく、うどんの製造と卸しをやっている業者で、おそらく多度津の「卸商」も製造卸だと思います。規模は「うどんを箱に入れて自転車でどこかへ卸しに行っていた」という程度のもので、卸す商品は、卸先で生麺から茹でるとは思えないので、おそらくゆで麺だと思います。
半夏生に手打ちうどん
「半夏生にうどんを食べる」という風習が、新聞記事にはっきりと出てきました。
今年は半夏生までに終わる? 三豊郡西南部の田植え
三豊郡西南部における今年の麦作は比較的小麦が多かったため多少収穫が遅れ気味であったが、天候もやや順調でそれぞれ庭揚げを終え、ひたすら滋雨の至るのを待っていたところ、18日午前0時頃からいよいよ梅雨が殺到して来たので、これをきっかけにどこも一斉に田植えを開始している。いつもならば半夏生後ならではとても足洗のできなかった同地方も、この向ならば半夏には手打ちうどんで安息の祝杯を挙げ得るだろう。
「半夏のうどん」に関する新聞の記述は、明治23年に「半夏にはうどんの4、6、10杯も食べる者がいる」と書かれていたのが初出(「明治20年代」参照)。しかしその後、明治41年と大正4年に掲載された「半夏生」を紹介する記事にはいずれも「うどん」が全く触れられておらず、風習の実態がよくわからないままでしたが、ここで「半夏には手打ちうどん」という記述が確定的に出てきました。「当たり前のことは記述されない」という歴史資料の原則からすると、「半夏生にうどんを食べる」というのは当時すでに当たり前すぎて「わざわざ書く必要がない」とされていたのかもしれません。
就職難でうどん屋を始めた大学生
年末に、当時のご時世が垣間見えるうどん関連記事が載っていました。
働くものの上に幸福と悦楽あり
香川県三豊郡萩原村出身の九大法学部の○○君が独自の生活哲学から福岡東中洲に「一平うどん」を開業
東博多中洲川丈座横の河中に突き出た露天街の中程に、「一平うどん」という風変わりな名前のうどん屋がある。店の女もうどん屋にしてはサッパリしすぎた七三の耳かくし、おっさんはまだ若くてせいぜい25~26、髪をきれいに分けて「一平うどん」と染出した法被を着ているのも何だか似つかず、素人臭いこの若いうどん屋さんは○○君といい、九大法文学部の学生で来春には法学士として巣立つ、いわば学士様の卵だ。「一平うどん」の「一平」は六高時代のニックネームを採ったのだという。
…(中略)…12月2日から開業した。開業祝いには学友達から醤油、酒などが寄贈され、小さな店を飾った。7日夜、これから夜鳴きに出かけようと車の仕度を整え、同君は語る。「人は何と言われるかしれませんが、現在の私としてはこれが一番正しい生活だと信じています。明日のことを思い患わないのが私の信条です。うどん屋を始めようと考え出してから約半ヶ月間、出前持ちの練習をさせてもらい、今ではもう一人前のつもりです、この車も280円ばかりかけて作りましたが、車に消毒釜を設備しています。夜鳴きで消毒釜を持っているのは博多中で私だけでしょう。店と夜鳴きとで毎日1円20~30銭の純益があり、私一人食うには充分です。お得意は場所がらだけに藝妓や女給さんで、社会の裏面もよくわかり、いい勉強ができます」
三豊郡萩原村(今の観音寺市大野原町)出身で九州大学を出た若者が博多で「一平うどん」といううどん屋(店舗と屋台)をやっているという話ですが、○○君が「人は何と言われるかしれませんが…」とか「私一人食うには十分」と語っているように、「うどん屋」は社会的にそれほど評価の高い職業ではなかったことが窺えます。そして、これが載った約2週間後に、今度はこんな記事が出ていました。
就職難の新卒業生 大学を出てうどん屋開業
(前略)…就職難にあえぐ九州大学生の間には街頭に進出して実社会の体験を得ようとする傾向がすこぶる高まってきて、現に法文学部の○○君は福岡市東中洲の盛場裏町で「一平うどん屋」を開業し、夜鳴きうどんで評判をとっており、同学部の△△君は夜はカフェー「ハナヤ」に住み込んで如才ない。
当時、九州大学の学生は「就職難に喘いでいて、就職せずに飲食店で働く学生がたくさんいた」とのことですが、この記事の前段には「就職難の新卒業生、文部省も大弱り」という見出しの記事が付いていたので、大学生の就職難は全国的なものだったようです。
昭和5年(1930)
香川県産品の概要が窺える記事が出てきました。
全国的に優良な本県産品 この際県民に周知せしめ、県が奨励に務める方針
国産振興委員会が大正15年に商工省内に設置されて以来、毎年全国的に優良国産品の調査を行っているが、最近ではその主なるもの百余種を得ている。当局ではこれを将来国内に周知せしめ、舶来品の爆圧を防止し、むしろ逆襲を加える方針である。本県においても全国的に優良な県産品が相当あるので、中央と歩調を一にして県民にこれを周知せしめ、大いに奨励に務めることになり、近くそれについて協議会を開く模様である。今、本県産にして優良国産品と見られているものを挙げると、大要次の通りである。
●醤油……………………(県産額)10916848円 (輸出額)8000000円 (輸出率) 73.3%
●小麦粉…………………(県産額) 4270212円 (輸出額) 331583円 (輸出率) 7.8%
●和酒……………………(県産額) 4266035円 (輸出額) 391594円 (輸出率) 9.2%
●和紙……………………(県産額) 3514865円 (輸出額)1744435円 (輸出率) 49.6%
●製帽用眞田……………(県産額) 1018160円 (輸出額) 738006円 (輸出率) 72.5%
●麦稈帽子………………(県産額) 800000円 (輸出額) 700000円 (輸出率) 87.5%
●農具……………………(県産額) 583280円 (輸出額) 46608円 (輸出率) 8.0%
●彫抜漆器………………(県産額) 494505円 (輸出額) 450000円 (輸出率) 91.0%
●燐寸……………………(県産額) 195816円 (輸出額) 95318円 (輸出率) 48.7%
●別珍……………………(県産額) 156412円 (輸出額) 156412円 (輸出率)100.0%
●莫大小(メリヤス)…(県産額) 91330円 (輸出額) 26120円 (輸出率) 28.6%
香川県が「優良県産品として周知奨励する」とされていたのがこのラインナップですが(輸出率は筆者が付記)、「うどん」がどこにも見当たりません。大正元年の記事で徳島県人の詐欺師が「讃岐名物のうどん」と言っていたように(「大正元年~5年」参照)、この頃すでにうどんは県外にも認知され、県内の流通量も相当多かったはずですが、何の理由で外されたのでしょうか。昭和54年に「県の経済労働部がまとめた地場産業23業種の中に製粉製麺業が入ってなかったことが県議会で問題視された」という騒動があり(「昭和54年」参照)、その時は当局が「担当部署が違って…」とか苦しい言い訳をしていたようですが、どうも昔は行政の中で、「うどん」の扱いについて何か迷走していたようにも感じます。ちなみに輸出率を見ると、県産額1位の「醤油」は7割以上が県外に販売されていますが、2位の「小麦粉」は90%以上が県内で消費されています。その需要はおそらく「うどん用」が大半ではないかと想像しますが、それでも県が周知奨励する「優良県産品」には入れてくれませんでした。
「半夏生」の記事に「うどん」の記述はなし
この歳の「半夏生」は7月3日でしたが、「農家が農作業を休む」とあるだけで、「うどんを食べる」という風習は特に書く必要もなかったのか、記述がありませんでした。
今日は半夏生
3日は半夏生で夏至からちょうど11日目にあたり、梅雨も明け、田植も昔からこの日で終わるとしており、農家では皆、この日は業を休むことになっている。
ちなみに、「半夏生」は「夏至から11日目」と決められていますが、夏至の日は年によって変わるので、必然的に半夏生の日も変わります。気象庁のデータによると、半夏生の日はだんだん前倒しになっていて、1980年代までは「7月2日」と「7月3日」が2年ごとに交代、1990年代以降は「7月2日」が断然多くなり、2056年から「7月1日」が出現し始めるとのことです。
うどんの値下げの話題が3本
つい数年前まで「うどん屋が理不尽な値上げをしている」とかいう記事が何本も出ていたのに、ここに来て「値下げ」の話題が3本も出てきました。おそらく、冒頭に記した「世界恐慌~昭和恐慌」の影響だと思いますが、まずは志度から。
うどんが安くなる 志度署管内の傾向
うどんが安くなった。東京も大阪も時代の趨勢で麺類の値上げをしているが、志度署管内の某店が突如うどんを4銭、2杯なれば7銭、3杯10銭に値下げしたので、他の店も競争的に一斉値下げをする傾向を示してきた。
東京や大阪の大都市圏で麺類の値上げをしているところへ、志度のうどん屋が突如値下げしてきたとのこと。これに刺激されて他の店も値下げに向かうという動きがあるそうで…
新たに組織した飲食店営業組合 志度署の斡旋で共同購買もし、大いに組合を利用
大川郡志度町某飲食店が現下の状態に鑑がみて他店に率先してうどんの値下げを断行してから、一部分では寄り寄り相談していたが今回機運熟し、志度署の斡旋と同町○○、△△両氏発起のもとに志度飲食店営業組合を組織し、7日午前8時から町内同業者14名が志度署に集合して具体的規約を附議した。同組合は、「目下、物価の下落に伴い従来のうどん1杯5銭を4銭に値下げするを始め、従来より以上器物の清潔調理の衛生を期するためには一方原料を安価に購入する必要あり」として、組合において毎月積立金を作って、これによって原料を共同購買する等、大いに組合を利用することを申し合せた。…(以下略)
結局「みんなで揃って値下げしよう」という方向に話がまとまって、しかし値下げするには原価を下げないといけないので、共同購入も睨んで組合が結成されました。しかし、先の記事では「東京も大阪も時代の趨勢で麺類の値上げをしている」とあって、全国的な業界の動きはよくわかりません。
続いて、琴平でも値下げの動きが。
琴平における豆腐値下げ 焼豆腐が1銭、うどんも4銭
琴平町の豆腐営業者は10日から一斉に値下げして、豆腐4銭、揚豆腐2銭、焼豆腐1銭となり、うどんも4銭となった。
「大学生の就職難」に「うどん等の値下げ」と、やはり景気は悪くなってきているみたいです。
夜鳴きうどんで「鍋のフタを取ってジャブジャブ洗う」
国勢調査の実情を取材したレポート記事の中に、夜鳴きうどんの様子が出ていました。
国勢調査の実情を探りに高松の深夜を歩く
(前略)…記者が内町から片原町に出ると、これが最後のような哀れっぽい夜鳴きうどんの爺さんが通る。記者が呼び止めると、すぐ鍋の蓋を取ってジャブジャブうどんを洗う。その職業意識の素早いこと。
「本職は大工ですが、今はうどん屋さんですよ。ですからちょっと、どう書いてよいか迷いましたが…」
「どう書きました」
「いーえ、これから帰って考えて書きます」
記者は「それならこう書きたまえ」と指示したかったが、爺さんが「帰って考える」というので沈黙した。国勢調査の申告書は自己反省を示す。世帯、出生年月日、配偶関係、職業、そのいずれもが過去から現在に、現在から未来への連鎖的想起である。夜鳴きうどん爺さんが「考えてから…」という一語は、単に申告書についてではなかろう。何かそこに人生探求の思索といったようなものがあるに違いない。…(以下略)
記者が夜鳴きうどんの爺さんに声を掛けたら、「客が来た」と思った爺さんが「鍋の蓋を取ってジャブジャブうどんを洗い始めた」とのこと。「うどんを洗う」というと、茹で上がりの「釜あげ麺」を水で洗う場面しか思い浮かびませんが、屋台で生麺から茹でていたとは思えないので「うどんを洗う用の水が入った鍋」ではなさそう。するとこれは「湯の入った鍋」で、「ゆで麺のうどん玉」をテボか素手で鍋の中の湯につけてさばいている」という状況を「ジャブジャブうどんを洗い始めた」と書いたのでしょうか。昭和2年の記事に「(夜鳴きうどんの青年が)沸騰する饂飩湯を全身にあびて…」とあったので夜鳴きうどん屋台の鍋には熱湯が入っていたと思われますが、記事からは曖昧な状況しかわかりません。それにしてもこの記者、「国勢調査の申告は自己反省を示す」とか「夜鳴きうどんの爺さんが国勢調査の申告を考えるのは、人生の思索があるに違いない」とか、何だか「夜鳴きうどん」という職業に対する“上から目線”が前提にあるようで、今なら炎上しそうな書き方です(笑)。
人助けは「うどん」で
「警察署員が貧しい人にうどんを食べさせた」というお話。
高松署員の情けで温いうどんと旅費を恵まれた、失業苦に喘ぐ男の哀話
15日午後8時頃、高松署の受付へ年齢34~35才の浮浪者風の男が辿りついて救いを求めたので、宿直の署員が問いただすと、同人は岡山県邑久郡幸島村の○○(34)で、本年8月21日、大分県臼杵町某セメント会社臼杵工場の雑役夫として勤務中、誤って右手を切断して不具者となったので、わずか2円30銭の涙金で同工場を解雇され、詮方なく職を求めて対岸愛媛県に渡り、その後、求めて得られぬ求職の漂泊を続けていたが、その間1日一度の食事もろくろくできず、故郷岡山へ帰るため高松に辿りついたが懐中にはわずか19銭を残すのみで帰るに帰れず、切羽詰まって高松署に救いを求めて来たものと判明したが、署員の情けで温かいうどんと宇野までの旅費を恵まれて立ち去った。
小さな美談の一つですが、考えてみると、同じような話が全国であったとしても「うどん」を食べさせるのは香川県ならでは、という気がします。出前でしょうか、署内に常備していたのでしょうか(笑)。