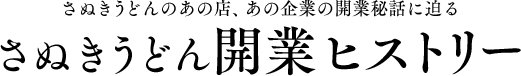全一話
玉藻
聞き手・文:萬谷純哉
お話:初代店主喜多博さんのご子息・喜多祐三さん(高松市中野町出身)
まずは、昭和34年の四国新聞に載ったこの記事をご覧ください。
連載「東京のさぬきっ子」 当てた”讃岐うどん” 喜田博氏(うどん店主)
「玉藻うどん」店主。都の西北、早稲田の森に一昨年から名物が一つ増えた。“玉藻よし”讃岐の国の住人、喜田氏の始めた手打さぬきうどんである。
35年間の教師生活に終止符の打たれた日、この人に残されたものは何がしかの退職金と、6人の幼い子供だった。もっとも、上の2人は東京へ遊学中だったが、子供たちの教育のためには、というので一家をあげて上京し、うどん屋を始めたわけである。その動機は光子夫人(54)が昭和25年から高松高校購買部の食堂でうどんを扱っていたので、ある程度の経験と自信があったから。
高松から職人も1人連れてきて学生相手に始めたのが当たった。東京のうどんが関西に比べてどれほどまずいのかということの証明のようなもので、ことに関西出身の早大生はこの店に来て郷愁を癒すようになった。自家製造のため店の裏に作った製めん所もすぐ手狭となり、現在雑司ヶ谷に移って職人も3人がかりでやっているが、至って好評。新宿、池袋の三越はじめ乾物屋へも卸しているが、すでに能力の限界と、うれしい悲鳴をあげている。在京県人の間でもよく知られてきたようで、遠く横浜あたりから定期的に通ってくる人もあるとか。今では次男の俊氏(27)がそれまでの勤めを止め、両親を助けて働いている。
この記事は本サイト内の「新聞で見る讃岐うどん」の「昭和34年」の項にも載っていますが、おそらくこの「玉藻」が、記録に残る「東京に初めて進出した讃岐うどん店」。この4年後の昭和38年の四国新聞に「東京の讃岐手打ちうどんの元祖は、高松市出身の鈴木力男さんが始めた『讃岐茶屋』」という記述がありましたが(「昭和38年」参照)、その4年前にこの「玉藻」に紹介記事が載っているので(記者がうっかりしていたのでしょうか)、明らかにこちらが先です。そしてこのたび、この「玉藻」の店主・喜田博氏のご子息の喜多祐三さん(昭和14年生まれ)に当時のお話をお伺いすることができました。ご子息が語る、ご両親の波瀾万丈のショートヒストリーです。
昭和20年代、父の仕事で八幡浜に移住
私は6人兄弟の末っ子ですが、実は両親が東京でうどん店を始めた時に3番目の兄がサポートで店に入っていて、両親が東京で讃岐うどんを始めることになった経緯や開業後の展開についての回顧録のようなものを残していたので、そのあたりの記録と私の記憶を元にお話しします。
父も母も明治生まれの讃岐人ですが、終戦後に父が最初に就いた仕事が愛媛県八幡浜市の女学校の音楽教師だったもんですから、家族みんなですぐに八幡浜に移りました。その頃は食べていくのが本当に大変な時代でしたが、八幡浜は漁港の町だったですからお魚をいろんなところでもらってきて、それを食べながらいろんなことをして生き延びていました。
特にうちは母がチャレンジ精神豊かな人で、オヤジの尻をひっぱたいて(笑)いろんなことをやってたようです。例えば、父の音楽教師の給料だけでは食べていけないと言うので、たぶん母が見つけてきたんだと思うんですが、リヤカーにポン菓子の装置がくっついているようなのを手に入れて、装置の中に米を入れて火をくべて燃やしながらぐるぐる回して、圧力が充満したところでボンとはぜさせて、米が膨れたところへ砂糖湯をかけてお菓子を作るあれな、そのポン菓子の製造装置を「あなたこれをひっぱって商売しなさい」と。父は学校のない平日の夕方以降と週末の日曜日にそれをひいて、大きな声で「ポン菓子屋~、ポン菓子屋~」って叫びながら歩いたわけだ。教師だからできるだけ教え子の家は避けて顔見られないようにやってたらしいんだけど、たまには見られて甚だバツの悪い状況になったこともあると思うんですが、とにかくそれをひいて副収入を得ていた。そんな苦労してるのを私は見てますから、子供心に生活が大変だというのはわかっていました。八幡浜にいたのは僕が小学校1年から4年までですが、そのポン菓子は2年くらいやっていたと思います。
香川に戻り、父は高校教師、母は高松高校の食堂で働き始める
その後、父は今度は香川の主基高校、今の農業経営高校の音楽教師として、ふるさとの香川県高松市に戻ってきました。それから飯山高校に移って、その後、高松女子商、たぶん今は高松商業と一緒になってると思うけど、当時は女子の学校だった高松女子商の先生になった。それが父が50歳くらいの時です。私は亀阜小学校に通うことになりました。
母は高松高校の食堂で働いていました。きっかけはよくわからないんですけど、高松高校の中庭にあった大きな楠の木のそばに食堂があって、母はそこに毎日出勤しておりました。そこで、母はダシをとって生徒さんにうどんを作って出していたらしい。当時、母が売れ残ったうどんとかだし汁とかを家に持って帰ってきて、それを自宅で食べたことはあります。ダシは煮干しと昆布だったと思うんですが、たくさんの学生にうどんを作って食べさせるわけですから、ダシをとった後の昆布も大量に残るわけですね。その昆布を母が持って帰ってきて、それを佃煮風にして味をつけて食べた。これがうまかった記憶があります。
家では父もうどんを作ってました。本格的なうどんじゃなかったけれども、父が簡単に麺棒で伸ばしてうどんらしきものを作って、しょっちゅう食べてました。外食のうどんは当時も「源芳」さんとか「アズマヤ」とかにおいしいうどんあったと思いますが、家でそうやっていつでもうどんが食べられたから、あんまり外にうどんを食べに行った記憶はないですね。
東京行きを決意
そうこうしているうちに、「東京に出てうどん店をやろう」という話が持ち上がってきたんです。その背景は僕には想像するしかないんだけど、まず、母が働いている高松高校の食堂に高松高校のOBで早稲田大学に通っている学生が時々遊びがてらにうどんを食べに来て、「東京のうどんはまずい」という話を母がしょっちゅう聞かされていたらしいんですね。そこで、元々“チャレンジ精神”があった母に、事業欲みたいなものがだんだん出てきたんじゃないかと思います。うどんについては高校の食堂で何年もやってますから大体の流れはわかっていただろうし、その時、たぶんうどん玉を仕入れていた「源芳」さんとも懇意になっていて、東京でうどん屋をやることについていろいろ相談したようです。
あと、家の事情としては、私は紫雲中学から高松高校に入っていて、卒業したらいずれ東京に行くことがわかっていました。上の兄弟はみんな県外に出ていたので、いずれ高松に父と母の2人だけが残ることになる。それならいっそのこと、家族みんなで東京に行ったらいいんじゃないかということになって、母が父に「私たちまだ50代だし、どう?」とか言って話を持ちかけたみたいです。まあいずれにしても「東京でうどん屋をやる」というのは母の着想で、父はどちらかというと母に尻を叩かれて動いたというところですかね(笑)。そういう経緯で、昭和32年の春、一家で東京に移りました。私は高松高校を2年で離れて、高校3年の1年間だけ東京の高校に行きました。
昭和32年、早稲田大学のすぐ横で「うどん食堂・玉藻」を開業
向こうに行ってすぐ、母が中心になってうどん屋開業の準備が始まりました。まず、肝心の「うどんの打ち手」は、母が「源芳」さんに頼んでうどん職人を紹介してもらいました。「源芳」の女将さんが母の情熱にほだされて、腕利きの職人を一人出してくれたんです。若い職人さんでね、源芳で修業しただけあってうどんの腕はよかった。ただ、職人ですから一本気なところがあってね、ケンカもするしルールは守らないし、突然いなくなったりして探し回ったり、警察沙汰になることも何度かあってね(笑)。父には信頼されていたんですけど、とにかく素行は悪かったなあ。それで、「腕はいいけど彼一人に頼っていたら困る」というので、3番目の兄が会社を辞めて、製麺を習って店に入ることになったわけです。結局その職人さんは途中でいなくなりましたけど(笑)。
これが、開店祝いでいろんな人が集まってくれた時に撮った写真です。
こっちは母と、最初に入ってくれた店員さんの写真ですね。
これは店の看板と、高校3年の時の私です。
貧乏学生に「安くてうまいうどん」を
そんなこんなで、店の裏手の掘っ立て小屋みたいなところで職人さんがうどんを打って、店は女の子の店員を入れて、母が中心になって切り盛りしながら店を始めました。店のメニューや値段については記録がないんですが、私の記憶では、メニューは素うどんにたぬきうどん、きつねうどん、肉うどん。肉うどんは牛肉を甘辛く煮たものをうどんにかけたものだったけど、かなり人気がありましたね。それから「おかめうどん」もあった。釜揚げもあったように思うんだけどなあ。うどんの他にはいなり寿司とか、カツ丼みたいな丼物もリクエストがあったら作ってたんじゃないかな。ただし、おでんはなかった。
値段は、素うどんが10円か15円ぐらいだったかな。肉うどんが確か30円くらい。うちの店の筋向かいにタンメン屋さんがあって、そこのタンメンのメニューが30円とか50円くらいだったから、とにかく「安いうどんを学生さんに食べさせていた」という印象がありますね。貧乏学生にはただで食わせたりしてたからね。そもそも東京にうどんを持って行こうと思ったきっかけの一つに「貧乏学生にもおいしいうどんを食べさせたい」という気持ちがあったから。それで早稲田の横に食堂を出したから、とにかく安く、貧乏学生でも食べられるような値段に設定したんだと思います。
「玉売り」の販路拡大で採算ベースに
ただし、そのせいで店はいつも赤字だったと思います。場所が早稲田大学のすぐ横だから客の大半が早稲田の学生で、一般のお客さんはほとんどいなかったと思うんですが、学校は春休みがあったり夏休みがあったり冬休みがあったりで、1年の半分くらいがお休みだよね。だから店自体は黒字になったことはたぶんないんじゃないかな。
そこで、「うどん玉の販売」の販路を広げるために兄がいろんなところに飛び込みで営業に行って、百貨店では池袋と新宿の三越、スーパーマーケットは新宿の今の「アルタ」があるところにあった「二幸」に卸せるようになりました。兄は最初の頃、自転車の荷台にせいろを10枚ぐらい積んで、早稲田から全部自転車で配達に行ってましたね。そうやってだんだん販路を広げていくうちに製造が追っつかなくなってきて、オープンの1~2年後に文京区の雑司が谷というところにちょっと大きな製麺所を作ったんです。職人も4~5人増えて、配達も軽トラで行くようになりました。これがその頃の写真です。
昭和34年には、新宿三越で讃岐うどんの実演販売もやりました。三越の食品販売の責任者の方に新しくなった製麺所を見てもらって、そこで試食もしてもらったら「これはうまいね」ということで、その三越の責任者に「じゃあ喜田さん、お客さんの前で打ってそこで即売するという新企画をしてくれないか」と言われてやることになったんです。まあそうやってね、製麺所の方も最初は初期投資の返済で苦しかったと思うけど、営業を頑張ったおかげで売上も伸びて、店の赤字をカバーしながら軌道に乗り始めたんですね。
ちなみに、オープンしてから四国新聞がうちを紹介してくれたんですけど、その時に四国新聞の白川さんという人にはずいぶんお世話になったそうです。四国鉄道管理局に佐々木正夫さんというっ方がいらっしゃって、この方も讃岐うどんには一家言持っていた方で、そういう方も白川さんから紹介いただいて兄はずいぶん人脈を広げることができて、いろいろアドバイスをもらったりしていたみたいです。
うどん事業を譲渡する
うどん店と製麺業を始めて5~6年経った頃でしょうか、高松の近藤さんという方から「共同経営をしたい」という申し出があったんです。近藤さんは、我が家が高松で家を建て替えた時に近藤さんの持っている離れに2カ月くらい住まわせてもらったという縁でいろいろお世話になった方で、以来ずっと親しくしていたんですが、四国新聞に載ったうちの店の記事を見て何か強い思いを持たれたようです。それで近藤さんが東京に出て来られて、結局、うどん事業を全部近藤さんに譲渡することになりました。それで我が家の東京でのうどん事業は終了しました。私の両親がうどん屋をやっていたのは、たぶん5~6年間だったと思います。近藤さんが買い取った後、うどんの事業がどうなったかというのは、私はちょっと情報を持ってないですね。
店を譲渡した時、父は確か61歳、母は5つ下だから56歳くらいで、父の年金で生活をし始めました。それまでは子どもたちを育てるのに精一杯で、うどん屋を始めてからもいつも資金繰りやら何やらで苦労をしていましたから、うどん事業を手放してから母が72歳で先に亡くなるまでの15年くらいが一番穏やかで幸せな日々を送ってたんじゃないかと思います。
ちなみに、父は61歳から手習いで水墨画を始めました。元々父は音楽より絵の才能の方が豊かだったようで、水墨画のいい先生に出会ったこともあって5年くらいで急激に頭角を現して、「喜田雲泉(きだうんせん)」という名前で日本の水墨画界で名の知れた画家にまでなりました。昭和30年代の終わり頃には、渋谷の表参道にオープンした「さぬき路」といううどん店の開店祝いに、すごく大きくて立派な水墨画を描いて贈っていましたね。父は92歳まで生きましたが、母が亡くなった後も、水墨画教室を8つくらいやってましたよ。生徒は有閑マダムをはじめほとんどがご婦人方で、「喜田先生、喜田先生」って大事にされてましたから、結構幸せに長生きできたんじゃないかな(笑)。
- [全一回]
- 全一話 玉藻 2021.07.08